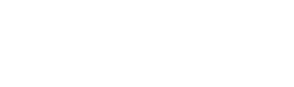共有不動産を処分しようと思い、他の共有者に連絡を取ろうとしたところ、共有者の一人と連絡が付かず、行方不明になっているというケースがあります。共有不動産の処分には、共有者全員の同意が必要になりますが、共有者が行方不明という場合には、どのように手続きを進めていけばよいのでしょうか。
今回は、共有者が行方不明で生じる問題点とその解決方法をわかりやすく解説します。
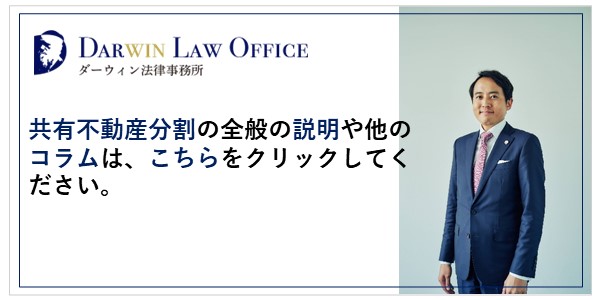
目次
1、共有不動産の共有者が行方不明で生じる問題とは?
共有不動産の共有者が行方不明になっている場合には、以下のような問題が生じます。
(1)共有不動産の売却ができない
共有不動産の売却や賃貸は、共有物の処分にあたりますので、共有者全員の合意がなければ行うことができません。共有者のうち1人でも行方不明になってしまうと、共有者全員の合意が得られず、共有不動産を売却することができなくなってしまいます。
(2)共有不動産の管理費用の負担を強いられる
共有不動産に限らず、不動産を所有していると草木の手入れや設備の補修など不動産を管理する手間が生じます。また、修繕費や固定資産税などの費用負担も生じますが、これらの手間や負担は、共有者の持分に応じて負担するのが原則となります。
しかし、共有者のなかに行方不明者がいる場合には、管理や負担を求めることができませんので、共有者のうちの誰かが肩代わりして負担しなければなりません。
(3)世代交代により権利関係が複雑になる
共有者が死亡して、相続が発生すると共有者の相続人が持分を引き継ぐことになります。相続で一人の相続人が共有持分を引き継いでくれればよいですが、複数の相続人による共有となれば、当初の共有関係よりも当事者が増え、権利関係が複雑になります。
そのような状況で共有者に行方不明者がいるとなれば、さらに権利関係は複雑なものとなるでしょう。
2、行方不明者がいる場合の解決法①|不在者財産管理人制度
行方不明者がいる場合の解決方法の1つ目として、不在者財産管理人制度というものがあります。
(1)不在者財産管理人制度とは
不在者財産管理人制度とは、行方不明者の代わりに財産管理を行う人(不在者財産管理人)を選任する制度のことをいいます。裁判所によって選任された不在者財産管理人が行方不明者に代わって、共有物の処分に関する同意をしてくれますので、共有不動産の売却などが可能になります。
(2)不在者財産管理人の選任の流れ
行方不明者について不在者財産管理人を選任する場合には、以下のような流れで行います。
①家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立て
不在者財産管理人を選任する場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。
●申立てができる人……不在者の利害関係人
●申立先の裁判所……不在者の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所
申立てにあたっては、以下の書類が必要になります。
●申立書
●不在者の戸籍謄本
●不在者の戸籍の附票
●不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
●不在の事実を証する資料
●不在者の財産に関する資料
●不在者と申立人との関係を示す資料
②家庭裁判所での審理・審判
裁判所に不在者財産管理人の選任申立をすると、提出書類の確認や申し立てのあった人が本当に不在者であるかの確認が行われます。
裁判所では、不在者財産管理人の候補者と不在者との関係、不在者の財産内容などを踏まえて、不在者財産管理人の選任の審判を行います。申立人が指定した候補者がそのまま不在者財産管理人に選任されるわけではありませんので注意が必要です。
③不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て
不在者財産管理人が不在者に代わってその財産を処分するためには、裁判所の許可が必要になります。この申立ては、共有不動産の共有者からではなく、不在者財産管理人が行います。
3、行方不明者がいる場合の解決法②|失踪宣告
行方不明者がいる場合の解決法の2つ目として、失踪宣告という制度があります。
(1)失踪宣告とは
失踪宣告とは、生死不明の人がいる場合には、法律上死亡したものとみなす制度のことをいいます。行方不明者について失踪宣告がなされれば、その人は死亡したものとみなされますので、行方不明者の共有持分を引き継いだ相続人との間で共有不動産の売却手続きを進めていくことができます。
なお、失踪宣告者に相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任し、相続債権者や受遺者への弁済、特別縁故者に対する財産分与がなされた後、他の共有者に失踪宣告者の共有持分が引き継がれます。
(2)失踪宣告の種類
失踪宣告には、以下の2つの種類があります。
①普通失踪
普通失踪とは、行方不明者が生死不明になって7年が経過した場合に認められる失踪宣告です。普通失踪では、生死不明となって7年が経過した時点で死亡したものとみなされます。
②特別失踪(危難失踪)
特別失踪とは、行方不明者が死亡する蓋然性の高い危難に巻き込まれた場合に認められる失踪宣告です。危難が去ったときから1年が経過した時点で申立てをすることができ、危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
(3)失踪宣告の流れ
行方不明者について失踪宣告をするには、以下のような手続きが必要になります。
①家庭裁判所に失踪宣告の申立て
失踪宣告をする場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。
●申立てができる人……行方不明者の利害関係人
●申立先の裁判所……行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立てにあたっては、以下の書類が必要になります。
●申立書
●行方不明者の戸籍謄本
●行方不明者の戸籍の附票
●行方不明者が失踪したことを証明する資料
●不在者と申立人との関係を示す資料
②家庭裁判所での審理・失踪宣告
失踪宣告の申立てがなされると、家庭裁判所の調査官により調査が行われます。
そして、官報や裁判所の掲示板で、行方不明者自身または行方不明者の生存を知っている人に対し、一定期間内に届け出るよう催告が行われます。催告期間は、普通失踪で3か月以上、特別失踪で1か月以上となります。
催告期間内に届出がなければ、裁判所により失踪宣告がなされます。
③市区町村役場への届出
家庭裁判所による失踪宣告がなされた後は、行方不明者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場で、失踪の届出を行います。これにより、失踪宣告がなされたことが戸籍に記載されます。
4、行方不明者がいる場合の解決法③|所在等不明共有者の持分取得・処分制度
行方不明者がいる場合の解決方法の3つ目として、所在等不明共有者の持分取得・処分制度というものがあります。
(1)所在等不明共有者の持分取得・処分制度とは
所在等不明共有者の持分取得・処分制度とは、裁判手続きにより、所在不明となっている共有者の持分の買取や共有持分を含めた不動産全体の処分が可能になる制度です。
これは、民法改正により令和5年4月1日から新たにスタートした制度ですので、知らないという方も多いかもしれません。近年、所有者のわからない不動産が増えてきており、空家問題も深刻化しています。このような所有者不明の不動産に関する問題を解決するために導入されたのが所在等不明共有者の持分取得・処分制度です。この制度を利用することで、共有者が所在不明であったり、共有者を特定できない場合でも裁判所の判断により、共有不動産の処分が可能になります。
(2)所在等不明共有者の持分取得・処分制度の利用方法
所在等不明共有者の持分取得制度では、所在等が不明な共有者がいる場合に、他の共有者に持分を取得させることができる制度です。また、共有者が共有不動産の処分を希望する場合には、所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度を利用することにより、所在等不明共有者の持分を処分することができます。これらの制度を利用する場合には、以下の要件を満たす必要があります。
●不動産が数人の共有に属すること
●他の共有者を知ることができない、または、その所在を知ることができないこと
●供託をすること
共有不動産の共有者から申立てがあった場合には、裁判所は、所在等不明共有者に異議申し立ての機会を与えるための公告を行います。3か月の公告期間に所在等不明共有者から異議の申立てがなければ、共有者の持分の取得または持分譲渡権限が付与されます。
なお、所在等不明共有者の共有持分が相続財産である場合には、相続開始から10年経過するまではこの制度を利用することはできません。
5、まとめ
共有不動産の共有者が行方不明になっている場合には、不動産の売却ができません。また、そのまま放置していると権利関係が複雑になりますので、早めに問題を解決する必要があります。
共有者が行方不明になった場合には、不在者財産管理人制度、失踪宣告、所在等不明共有者の持分取得・処分制度を利用することにより問題の解決が可能です。いずれの方法が最適であるかについては、個別具体的な状況によって変わってきますので、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
ダーウィン法律事務所では、不動産に強い弁護士が、共有不動産の取り扱いに力を入れています。共有不動産についてお悩みがある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
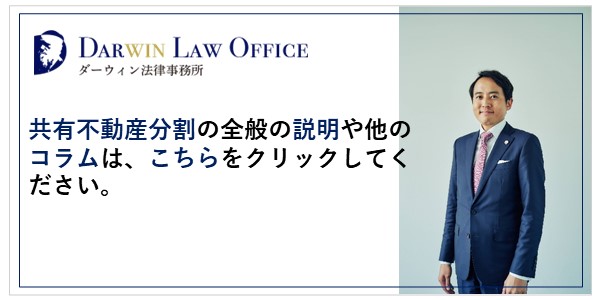
この記事を監修した弁護士