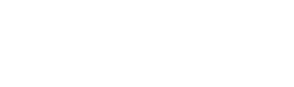マンションやアパートなどの賃貸物件を共有という形で所有している方もいると思います。共有名義の不動産では、単独所有の不動産に比べてさまざまな制約が生じますが、それは賃貸の場面でも同様です。
共有不動産を賃貸に出している方やこれから賃貸に出そうとお考えの方は、共有であることの特性を理解したうえで対応することが大切です。
今回は、共有不動産を賃貸する方法や賃貸をする際の注意点などについて解説します。
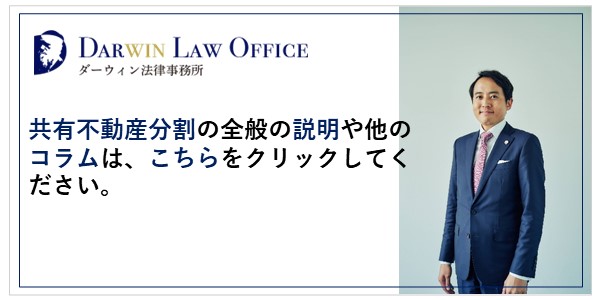
目次
1、共有不動産に関する3つのルール
共有不動産には、以下の3つの基本的なルールが定められています。共有不動産の賃貸を理解するためにも、まずは以下の3つのルールを押さえておく必要があります。
(1)保存行為
保存行為とは、共有不動産の物理的な現状を維持して、他の共有者に不利益を及ぼさない行為をいいます(民法252条ただし書)。具体的には、以下のようなものが保存行為に該当します。
●修繕
●腐敗しやすい物の売却
●無権利者に対する明渡請求、抹消登記請求
●法定相続登記の申請
このような保存行為に該当するものについては、各共有者が単独で行うことが可能です。
(2)管理行為
管理行為とは、共有不動産の性質を変えない範囲の利用行為や改良行為をいいます(民法252条本文)。具体的には、以下のようなものが管理行為に該当します。
●目的物の使用方法の決定
●賃貸借契約の締結、更新(ただし、一定範囲内のものに限る)
●賃貸借契約の解除
●賃借権譲渡の承諾
●一般的賃貸借の賃料変更
このような管理行為に該当するものについては、共有者の共有持分の過半数で決することになります。
(3)変更・処分行為
変更・処分行為とは、共有不動産の物理的変化を伴う行為や法律的に処分する行為をいいます(民法251条)。具体的には、以下のようなものが変更・処分行為に該当します。
●物理的な処分(消費、廃棄など)
●物理的な損傷
●土地の造成
●土地上への建物の建築
●建物の大規模な改修、建替え
●所有権を失う契約(売買契約、贈与契約など)の締結
●短期賃貸借の期間を超える賃貸借契約の締結
●借地借家法の適用がある賃貸借契約の締結
このような変更・処分行為に該当するものについては、共有者全員の同意が必要になります。
2、共有不動産を賃貸する方法
共有不動産を賃貸するにはどのような方法があるのでしょうか。以下では、共有不動産を賃貸する方法について説明します。
(1)短期間の賃貸借契約
短期間の賃貸借契約とは、以下の目的物および期間で行う賃貸借契約を指します(民法602条)。
●樹木の植栽または伐採を目的とする山林の賃貸借……10年
●それ以外の土地の賃貸借……5年
●建物の賃貸借……3年
●動産の賃貸借……6か月
このように短期間の賃貸借であれば、他の共有者に与える影響は小さいことから、共有不動産の変更・処分ではなく、管理行為にあたると考えられています。そのため、建物であれば3年以内、土地であれば5年以内の期間を定めた賃貸借契約を締結する場合には、共有者の過半数の同意があれば足りることになります。
ただし、実際には、建物の賃貸借や建物所有を目的とした土地の賃貸借については、後述する借地借家法の適用がありますので、すべての共有者の同意が必要になるケースが多いです。
(2)借地借家法の適用がある賃貸借契約
建物所有を目的とした土地の賃貸借と一般的な建物の賃貸借については、借地借家法が適用されます。
借地借家法では、弱い立場にある借主を保護するために、民法の賃貸借の規定よりも借主に有利な内容が定められています。そのため、借主から解約の申し入れがない限りは、貸主から賃貸借契約を終了させるのは難しいものとなっています。
このように借地借家法の適用がある賃貸借契約は、簡単には終了させることができないことから、賃貸借契約の締結は、変更・処分行為として扱われます。つまり、共有者全員の同意がなければ、借地借家法の適用がある賃貸借契約を締結することができないのです。
(3)長期間の賃貸借契約
長期間の賃貸借契約とは、前述した短期間の賃貸借契約の期間を超える賃貸借契約をいいます。このような長期間の賃貸借契約を締結すると、長期間契約に拘束され、不動産の利用処分が困難になることから、共有不動産の管理行為ではなく、変更・処分行為に該当します。
そのため、長期間の賃貸借契約を締結するためには、すべての共有者の同意が必要になります。
3、共有不動産を賃貸する際の注意点
共有不動産を賃貸する際には、以下の点に注意が必要です。
(1)不動産収益の配分が必要
共有者間で特別の定めをしていない限りは、賃貸不動産から生じた賃料は、共有者の共有持分に応じて分配する必要があります。共有者の1人が賃貸不動産から生じた賃料を独占していると、他の共有者から不当利得であるとして、返還請求をされる可能性もありますので注意が必要です。
なお、共有不動産の賃料は、共有者のうち1人を代表者と定め、その人が賃借人から全額を受け取り、他の共有者に配分するという方法が一般的です。賃借人に共有者の持分ごとの賃料を支払うよう求めることも理屈上は可能ですが、非常に煩雑な作業となりますので、それに応じてくれる借主はほとんどいないでしょう。
(2)確定申告が必要
共有不動産を賃貸すると賃借人から賃料を受け取ることができます。この賃料は、不動産所得に該当しますので、所得税の確定申告をする必要があります。
家賃収入が年間20万円以上ある場合には、たとえ賃貸経営が赤字であったとしても確定申告が必要ですので、忘れずに申告を行うようにしましょう。確定申告が必要であるにもかかわらず、それを怠った場合には、延滞税や無申告加算税というペナルティが課されることになりますので注意が必要です。
(3)賃貸借契約を解除するには過半数の同意が必要
賃借人による賃料不払い、用法遵守違反などがあった場合には、賃貸借契約の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することができます。
しかし、共有不動産の賃貸の場合には、賃貸借契約を解除する際にも一定の制約があり、共有者の持分の過半数の同意がなければ賃貸借契約を解除することができません。賃借人による債務不履行があれば、共有者全員に不利益が及びますので、賃貸借契約の解除に反対する人はいないとは思いますが、後日、契約の解除が無効だったと言われることがないように他の共有者の意向なども確認してから行うことが大切です。
4、共有者が不動産の賃貸に反対した場合の対処法
共有不動産を賃貸する場合には、共有者全員の同意または共有者の持分の過半数の同意が必要になります。一部の共有者が反対しているために賃貸を行うことができない場合には、以下のような対処法を検討しましょう。
(1)共有持分の買い取り
共有者の共有持分は、他の共有者の意向にかかわらず自由に処分することができます。共有者が不動産の賃貸に反対している場合には、その共有者に持分の譲渡を打診してみるとよいでしょう。
賃貸に反対している共有者の持分を買い取ることができれば、共有不動産の賃貸借契約締結の条件を満たし、賃貸をすることが可能になります。ただし、賃貸に反対する共有者の持分を強制的に買い取ることはできませんので、買い取りに反対された場合にはこの方法では困難です。
(2)共有持分の売却
共有不動産を賃貸に出せないのであれば、固定資産税や管理費などの負担がかかるため、手放してしまいたいという方もいるかもしれません。
共有不動産全体を売却するためには、すべての共有者の同意が必要になりますが、共有者の共有持分であれば、単独で売却することができます。
他の共有者や買い取り業者などの持分を売却することができれば、面倒な不動産の共有状態から離脱することが可能です。ただし、共有持分だけの売却では、完全な所有権を取得することができませんので、買い手を見つけることが難しく、見つかったとしても相場よりも低い金額でしか売却できない可能性がありますので注意が必要です。
(3)共有物分割請求
一部の共有者が反対しており、共有不動産の賃貸ができないという場合には、共有物分割請求を行うのも有効な手段となります。
共有物分割請求とは、共有不動産の共有状態の解消を求める手続きであり、以下の3つの方法があります。
●当事者の話し合い
●共有物分割請求調停
●共有物分割請求訴訟
共有不動産は、他の共有者の意向によっては利用や処分が著しく制約されてしまいますので、共有状態に不都合を感じる場合には、共有物分割請求を検討するようにしましょう。共有物分割請求をするにあたっては、共有不動産の問題に詳しい弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼をすれば、本人に代わって他の共有者との交渉や調停・裁判といった法的対応も任せることができます。
5、まとめ
不動産を賃貸する際にも共有不動産であった場合には、共有者全員の同意や持分の過半数の同意がなければ賃貸借契約を締結することができません。放置している不動産を有効活用するために賃貸を考えていたとしても、他の共有者の意向次第では、それも難しいケースも少なくありません。
共有不動産を放置していても税金や管理費用などの支出ばかりでメリットはありません。共有不動産の有効活用をお考えの方は、専門家である弁護士に相談をして、共有物分割請求の手続きを進めていくとよいでしょう。
ダーウィン法律事務所では、共有不動産の取り扱いに力を入れています。共有不動産についてお悩みがある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
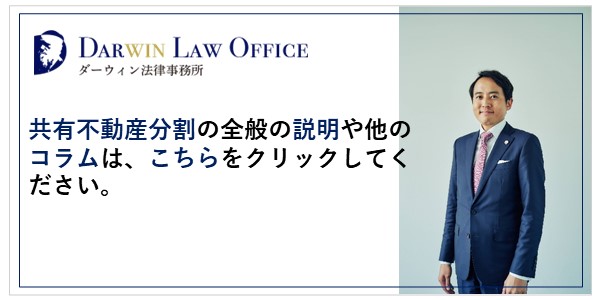
この記事を監修した弁護士